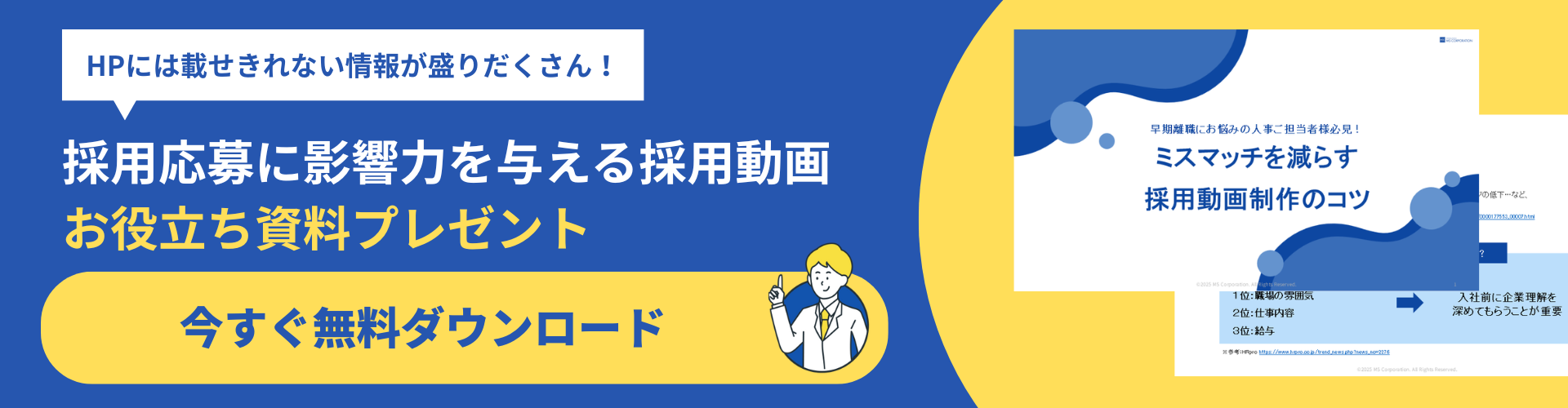高卒採用で知っておくべきルールとは?失敗しないためのポイントを解説

近年、高卒者を採用する企業が増加しています。一方で高卒採用には、企業側にも学生側にも守るべき独自のルールやマナーがあることはご存じでしょうか。一般的な中途採用や大学生の新卒採用とは異なり、応募方法や選考スケジュール、学校とのやり取りなどに特有の決まりごとが存在するため、基本ルールや注意点を理解しましょう。この記事では、高卒採用のルールとポイントを分かりやすく解説します。
目次
高校採用の現状
近年、高校新卒者を対象とした求人倍率は増加の傾向にあります。以下は、2021年度から2025年度における高校新卒者の有効求人倍率です。年々、上昇傾向にあることがお分かりになるでしょう。
| 年度 | 求人倍率 |
|---|---|
| 2021年度 | 2.08倍 |
| 2022年度 | 2.38倍 |
| 2023年度 | 3.01倍 |
| 2024年度 | 3.52倍 |
| 2025年度 | 3.70倍 |
参照:厚生労働省の資料より抜粋
これは少子高齢化や働き方の多様化などにより、企業の採用が年々難しくなっていることが挙げられます。今後も競争率が高くなると予想されている大卒の採用活動以外に、高校新卒者の採用にも力を入れる企業が増えているのです。
これまで高校新卒者に消極的だったITやサービス業でも、地方拠点の増加を背景に地元の高校生を採用する流れが広がっています。高校新卒者は就職が早いため、従業員である期間が長くなります。さらに後述しますが採用活動のルールが厳しく、できることが限られている分、採用にかかる費用も低コストです。こうした状況から、高卒採用のニーズは今後さらに伸びていくでしょう。
高卒採用におけるルール
高卒採用には独自のルールが多数存在し、企業はそれを正しく理解し遵守する必要があります。書類の形式や選考方法、スケジュールなど、大卒採用とは異なる制約が多いため、基本を押さえたうえで丁寧に対応をしましょう。
ここでは、高卒採用におけるルールを分かりやすく解説します。
1人1社制
高卒採用における「1人1社制」とは、応募解禁から一定期間、学生が応募できる企業を1社に限定するルールです。これは指定校求人に適用され、生徒は学校の推薦を受けて1社にのみ応募し、結果が出るまで他の企業に応募ができません。
この制度により、企業には志望度の高い学生が集まりやすく、内定後の辞退リスクが低くなります。学生は、学業と並行しながら効率よく就職活動を進められるメリットがあります。
ただし、地域や学校によっては運用やルールが違う場合があるため、企業は自治体・各高校のルールについて事前に確認しましょう。
企業からの直接交渉を禁止
高卒採用では、企業が学生に直接連絡を取ることは禁止されています。電話やメールはもちろん、SNSなども含めた接触が制限されており、学校を通じて連絡を行わなければなりません。また、職場見学や面接のスケジュール・合否に関する連絡なども同様です。生徒は学校生活に集中し、過度なプレッシャーを避けることが目的になります。
企業はこのルールを理解し、学校との信頼関係を築いた上で適切にアプローチする姿勢が求められます。
応募書類の統一
高卒採用では「全国高等学校統一応募書類」の使用が必須です。これは文部科学省、厚生労働省、全国高等学校長協会間で作成され、公正で差別のない選考を目的とされています。
学校側が調査書を作成する必要があり、履歴書や学業成績、人物評価を記載します。企業が独自の様式を求めることは禁止されており、毎年最新の様式を使用する必要があります。記載内容は定期的に変更されるため、採用を検討する担当者はしっかりチェックを行いましょう。
書類のみでの選考は禁止
高卒採用においては、書類のみで選考を行うことは禁止されています。必ず面接を実施し、必要に応じて適性検査や一般常識テスト、論文などを取り入れて、応募者を多面的に評価することが求められます。
書類だけでは把握できない人柄や仕事に対する意欲、将来性などを見極めるためにも、対面で話す機会を設けることが重要です。学力や成績以外の側面からも評価する必要があるため、より丁寧な選考が求められます。
採用フローは厳守
高卒採用では、厚生労働省や文部科学省・全国高等学校長協会などの協議により、応募開始日や内定日などの採用スケジュールが厳格に定められています。このスケジュールに基づいて企業は選考活動を進める必要があり、解禁日前の活動や内定の通知などは一切禁止です。 一部の大卒採用においてはスケジュールの形骸化が進んでいますが、高卒採用では違反行為とみなされるため厳守が求められます。
採用活動を成功させるためには、毎年更新されるスケジュールを事前に確認し、正確な情報に基づいて準備を進めることが大切です。学校や生徒との信頼関係を築くためにも、公正で適切なプロセスを遵守し、透明性のある採用活動を行いましょう。
定校求人の3倍ルール
高卒採用における「指定校求人の3倍ルール」とは、採用人数に対して最大でその3倍までの高校に求人票を送ってよいとする業界内の暗黙の慣例です。法的拘束力はありませんが、これを大きく超えると高校側に不信感を与えるおそれがあります。信頼関係を築くためにも、ルールに沿った運用が重要です。
地域によってはこのルールが存在しない場合もあるため、必ず事前に確認してください。
高卒採用のスケジュール
高卒採用には、スケジュールを含めて厳格なルールが存在します。それでは高卒採用は、一般的にどのようなスケジュールで行なわなければならないのでしょうか。ここでは、学生側・企業側の両方の主なスケジュールを紹介します。ルール違反や出遅れがないよう、きちんと把握しておきましょう。
学生側のスケジュール
高校生の就職活動は、2年生の終盤から段階的にスタートします。1〜3月には三者面談や求人情報の調査を行い、進路についての方針を固めます。 3年生の4〜6月には就職説明会に参加し、業界や職種についての理解を深めるタイミングです。7〜8月は職場見学や企業選定、求人票の確認を進め、9月にはいよいよ応募書類を提出します。9月末以降は一次選考の結果をふまえ、必要に応じて二次募集への応募を行います。
先述した通り、細かいスケジュールは毎年変動するので、都度確認し計画を立てることが大切です。
| 時期 | 活動内容 |
|---|---|
| 高校2年1~3月 | ・三者面談 ・求人情報の調査 |
| 高校3年4~6月 | 就職説明会への参加 |
| 高校3年7~8月 | ・職場見学や企業の選定 ・求人情報の調査 |
| 高校3年9月 | 応募書類の提出 |
| 高校3年9月末~11月中旬 | 二次募集への準備と応募 |
企業側のスケジュール
企業の高校採用活動は、毎年ほぼ決められたスケジュールに沿って進められます。
6月1日にハローワークへ求人申込書を提出し、7月1日から高校への求人票送付と学校訪問が可能になります。9月5日から応募書類の受け取りが始まり、9月16日には面接の選考活動と内定出しなどが解禁されるスケジュールです。 9月中旬以降は二次募集の準備を進め、10月から11月中旬にかけて二次募集の選考を行うことが一般的です。企業側のスケジュールも、毎年変更が無いか都度確認を行うことが大切です。
| 時期 | 活動内容 |
|---|---|
| 6月1日 | ハローワークに求人申込書を提出する |
| 7月1日 | 高校への求人申し込みと高校訪問が解禁 |
| 9月5日 | 高校から企業への応募書類の提出が解禁 |
| 9月16日 | 面接を含む選考活動と採用内定が解禁 |
| 9月中旬から末ごろ | 二次募集の準備 |
| 10月から11月中旬ごろ | 二次募集の開始 |
高卒採用で失敗いないためのポイント
高卒採用で優秀な人材を確保するには、限られた接点のなかで信頼を構築する必要があります。高校生本人との直接的なコミュニケーションを密に取ること、進路指導に関わる先生や保護者の理解と信頼を得ることも大切です。さらに、自社の魅力をHPやSNSを通じて発信することで、学生の志望度を高める有効な手段となります。
採用活動を成功に導くには、こうしたポイントを意識した戦略的な取り組みが必要です。現在、エムズコーポレーションでは採用動画に関するお役立ち資料を無料プレゼントしています。
高校生と直接会える機会を大切にする
高卒採用では企業から学生への直接連絡が原則禁止されているため、対面で学生と接点を持つ機会が大切です。
合同企業説明会やインターンシップ、職場見学の場では、学生に自社の魅力や雰囲気をしっかり伝えられます。こうした機会は、企業理解を深め、学生に安心感や興味を持ってもらうための貴重な場です。特に合同説明会では、多くの高校生に一度にアプローチできるため、効率的な認知向上につながるでしょう。また、地域によっては行政や商工会議所が開催する説明会があり、積極的に参加することで採用成功のチャンスが広がります。
学生との接点を計画的に設けることが、高卒採用における大きな鍵です。
先生や保護者へのアピールを重視する
高校生の就職活動では、進路指導を行う先生や保護者の影響力が非常に大きく、彼らの信頼を得ることが採用成功の近道です。大卒採用と異なり、生徒自身が主体的に動きにくいため、企業は先生や保護者に安心感を与えることが重要です。
「職場環境の安全性」「教育・研修体制」「卒業生の定着率」などを分かりやすく伝えることで、企業への信頼感を獲得できるでしょう。パンフレットや採用サイトで先生・保護者向けの情報を発信することも有効です。説明会で担当者の顔が見える対応をすれば、より好印象を与えられます。
自社サイトやSNSを活用する
若年層へのアプローチにおいて、自社サイトやSNSの活用は非常に効果的です。
高校生はスマートフォンを使って情報収集を行うため、InstagramやTikTokなどのSNSを通じた発信が自社の認知度向上につながります。コストを抑えながら情報発信ができるうえ、SNS投稿やショート動画など視覚的に訴えるコンテンツで魅力を伝えることが可能です。
▶採用動画制作の詳細はこちら
保護者や先生が閲覧することを想定し、高卒採用を目的とした採用専用サイトの作成や採用情報の専門アカウントを開設することもおすすめです。
▶採用サイト制作の詳細はこちら
まとめ
高校採用では、大学とは違い、応募書類や選考方法・採用スケジュールに関して厳格なルールが設けられています。これらを正しく理解し、守ることが重要です。 さらに、学生への直接的なアプローチが制限されているため、説明会やインターンシップなどの対面の機会を活かす工夫が求められます。 また、先生や保護者への情報提供、自社サイトやSNSの活用も効果的です。